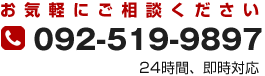伝聞証拠 ~伝聞証拠禁止の法則と反対尋問権~
百聞は一見にしかずということわざがある。他人から伝え聞くよりも、自分で直接、見た方が遙かに真実に迫ることができるという意味である。
確かに、又聞きというのは誤解を生じやすい。例えば友人Aから、「友人Bが私の悪口を言っている」などと言われても、実際に友人Bに確かめてみると、全然違うつもりで発言したことが、いつの間にか悪口だということにされていた、といった類いの体験は、誰でも一度は経験したことがあるのではないだろうか。最近は、SNS経由で不確実な情報が広く拡散されているので、そうした伝言ゲームの構造に注意すべきは当然である。
さて、悪口を言ったとか言わないとか言うレベルであれば、後から事実関係が明らかになったところで対処すればよい。しかし、これが刑事事件だと一大事である。不確かな情報を根拠に、人を処罰することがあってはならないわけである。
このような観点から、憲法は、被告人に反対尋問権を保障している(憲法37条2項)。つまり、誰かが何かを言っている、という証拠(供述証拠という)については、原則として反対尋問を行い、間違いがないかをチェックする機会を与えなければならない、ということである。
反対尋問というと、後にアメリカの大統領になる、アブラハム・リンカーンの若き日の逸話が有名である。リンカーンは、ある殺人事件の裁判で、証人が殺人の現場を目撃した、と証言したのに対して、現場には明かりがなかったはずなのに、どうやって現場が見えたのかなどと尋ね、月明かりで見えたという証言を引き出した上で、暦を取り出し、月の出の時刻という客観的な事実と矛盾することを示した。これによって、証人がウソをついていることを看破したわけである。もし、この証人が、殺人の現場を見たとだけ証言し、そのまま言いっ放しの状態であれば、被告人は有罪とされていたであろう。
さて、この、反対尋問権の保障という観点から、刑事訴訟法は「伝聞証拠禁止の法則」という原則を採用している(刑訴法320条)。これは文字通り、伝聞、すなわち又聞きの証拠は、刑事裁判の証拠とすることはできない、というものであり、例えば証人Xが、「証人Yは『被告人がZを殴っているのを見ました』と言っていました」と証言したところで、被告人がZを殴っていたことの証拠とすることはできないというものである。それは、証人Yが犯行を目撃した状況とか、YとZの関係性などについて、Yから直接、話を聞く機会というものを与えなければならない、すなわち、Yの反対尋問を行う機会を保障しなければならないからである。
また、刑事裁判では、多くの場合、警察官や検察官が供述調書を作成する。これは、捜査官が被告人や目撃者などから話を聞き取り、聞き取った内容を文章にまとめたものであるので、これを見ただけでは言いっ放しの状態である。やはり、調書の内容について、反対尋問を行う機会を与えなければならないわけである。
また、反対尋問権の保障以外にも、書面や又聞きを証拠とするより、法廷で直接、証人の言葉をきいたほうがわかりやすく、間違いが少ないということも、伝聞証拠禁止の原則の持つ重要な意味である。まさに「百聞は一見にしかず」であり、直接主義と呼んでいる。裁判員裁判などでは、反対尋問を行う必要が特になくても、裁判員への理解のしやすさという観点から、あえて証人尋問を行うような場合もあり、これは直接主義を重視した結果である。
かつて、我が国で戦犯と呼ばれる人たちを裁いた「東京裁判」という裁判が開かれたことがある。この裁判では、多くの伝聞証拠が採用され、伝聞証拠に基づいて有罪判決が多数、下されたと言われている。唯一、全員無罪の意見を述べたインドのラダ・ビノード・パール判事は、このことを厳しく指摘していた。
ネットの普及により、自分の目で見て、耳で聞く、という体験が失われつつあることは否定できない。また、情報源について深く考えることがないまま、いい加減な情報を安易に拡散してしまうことでトラブルに発展することもしばしばである。もちろん、多くの情報に触れる機会があるというのはよいことである。ただ、そのことと引き換えに、何が本物であるかが見えにくくなっている、このことは十分、意識しておく必要がある。

その他のコラム
【法科大学院生 司法修習生 若手弁護士必見】ヤバい事務所に気をつけろ! Part1

Part1 ヤバい事務所のヤバすぎる実像 セクハラ、パワハラ、オーバーワーク・・・ 世の中には、入ってはいけない弁護士事務所が厳然と存在する。 それは、スタッフの基本的人権を無視し、人間の尊厳をないがしろにするような職場だ。 そのような職場は、経営者に問題がある。 Part.1では、実際にあった事例を踏まえ、「ヤバい事務所」の実態を解説する。 リンク...
個人情報流出に備える LINEヤフーも明日は我が身

日本人の多くが利用しているYahoo!とLINEが、個人情報流出で揺れている。 LINEヤフーの個人情報流出 韓国経由で不正アクセス、44万件か(朝日新聞デジタル) - Yahoo!ニュース LINEヤフーは27日、LINEアプリの利用者情報など計約44万件の個人情報が外部に流出した恐れがあると発表した。うち39万件は実際の流出を確認した。大株主・韓国IT大手ネイバー傘下企業の委託先がnews.yahoo...
続報 持続化給付金詐欺 の判決まとめ3 不可解な地域差 20210703
はじめに 一般の方や、全国で持続化給付金不正受給の弁護人をされる先生方の参考になるよう、持続化給付金の判決について、分析を続けているところ、前回の記事から、さらにいくつかの判決に関する情報を入手した。 これまでの過去記事は以下をご覧いただきたい。 続報 持続化給付金詐欺 の判決まとめ2 20210616 【速報】 持続化給付金詐欺 の判決まとめ 20210429 前回から約半月であるものの、これまでの傾向...
続報 持続化給付金詐欺 の判決まとめ9 第一波と第二波の端境期

はじめに 持続化給付金の不正受給について、一般の方や、全国で同種事案の弁護人をされる先生方の参考になるよう、持続化給付金の判決について、情報収集を行い、分析を続けている。前回の記事から、さらにいくつかの判決に関する情報を入手した。 これまでの過去記事は以下をご覧いただきたい。 続報 持続化給付金詐欺 の判決まとめ8 役割分担の評価の難しさ 続報 持続化給付金詐欺 の判決まとめ7 小康状態は捜査の遅延か 続...
最決令和7年2月26日令6(行フ)1号 タクシー運賃の法規制の在り方

事案の概要 特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法は、タクシーの供給過剰に対処するため、国土交通大臣が「特定地域」「準特定地域」を指定し、道路運送法所定のタクシー運賃にかかる規制の特例を認めるものである。 Xはタクシー事業者であるところ、特措法により令和4年10月11日に国土交通大臣が料金の引き上げを行った(適用は同年11月14日)のに対し、引き上げ後の下限を下...