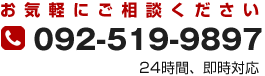少年法改正に関する問題点
これまでの議論の経過
現在、少年法改正の議論が進められているが、これは元々、民法の成人年齢引き下げや、選挙権を与える年齢を18歳としたことに伴って、少年法の適用年齢も引き下げるべきではないかという議論に端を発している。しかし、これに対して反対意見が根強かったため、最終的に、妥協の産物として、①18歳、19歳の少年については逆送の範囲を拡大し、②逆送されて刑事事件となった場合に実名報道を解禁する、という内容で改正がなされようとしている。
しかしながら、そのような考え方は、そもそも理論的に首尾一貫しないものであるし、過去の少年法の改正経過を踏まえないものであり、根本的におかしなものとなっている。
理論的な不整合
そもそも、少年法の適用年齢を何歳にするか、という問題と、逆送の範囲をどう定めるか、という問題は、理論的には全く別物である。前者の議論から後者の議論に移り変わること自体が、理論的に間違っている。実名報道の可否などはさらに別物の議論である。このことが混然一体と議論されていること自体が、既に議論自体のナンセンスさを物語っている。
逆送とは
逆送とは、少年法20条に基づいて家庭裁判所が少年事件を検察官に送致し、成人の刑事事件と同様に取り扱うものとする手続のことを言う(実際は、途中で二十歳になった場合や、実は二十歳を超えていた場合にも逆送がされるが、今回の議論とは関係ないので、以後、こちらについては省略する)。
逆送の要件としては、保護処分(保護観察や少年院など)よりも、刑事処分が相当であるといえる場合と定められており、一般的には、保護処分による改善更生が期待できるかどうか、保護処分による改善更生を行うことが社会的に許容されるかどうかを検討の上、決めることとされている。
但し、現実には、逆送事件のほとんどは、交通違反などでほぼ確実に罰金刑が見込まれる場合に行われる「罰金見込み逆送」と呼ばれる類型であり、他には、既に複数回、少年院送致になったことがあり、これ以上、保護処分による教育的なアプローチを試みても効果がなさそうな場合や、事件の経緯や動機などから見て、通常の成人事件と何ら変わりがない場合などに実施される傾向にある。そこでは、事件自体の重大性は、そもそも考慮の対象外であったり、考慮要素のひとつに過ぎないことが多い。実際上も、窃盗や傷害、詐欺などでの逆送事件が散見されるところである。
2000年少年法改正によるいわゆる「原則逆送」
しかし、1990年代後半の少年による重大事件やそれを受けた世論の後押しを受けて、2000年に少年法改正が行われ、逆送の対象年齢を16歳以上から14歳以上まで引き下げると同時に、故意の犯罪行為で人を死亡させた16歳以上の少年については、「調査の結果、犯行の動機及び態様、犯行後の情況、少年の性格、年齢、行状及び環境その他の事情を考慮し、刑事処分以外の措置を相当と認めるとき」を除いては、逆送しなければならないとする少年法20条2項を規定するに至った。
これにより、改正前に比べて、殺人や傷害致死などの逆送率は大きく上昇したのであるが、それでも、「原則」という言葉とは裏腹に、実際の逆送率は、罪名にもよるが40%~60%程度になっている。
実際上も、保護処分による改善更生に委ねるべきかどうかは、事件自体の重大性によって左右されうるものではないことが多く、事件自体の重大性で線引きをすることには「異物感」が否めないところである。少年の場合、未熟さ故に予想外の結果を招いてしまう、ということは往々にしてあり、その際に結果責任を問うことは、本来、少年法の要求するところではないのである。
逆送範囲拡大のもたらすもの
今回の改正では、原則逆送の範囲を、短期1年以上の法定刑が規定されている事件にまで拡張するということであるが、そうなると、前述の「異物感」はますます強くなることであろう。これは、成人の刑事事件における量刑の考え方を、少年法に無理矢理当てはめようとしている発想であり、理論的に無理があると言わざるを得ない。
また、実務上、逆送範囲拡大より、様々な悪影響が懸念される。
事実関係を争う事案の増加可能性
まず、例えば、改正案では、強盗罪は原則逆送事件に該当するとされているが、そうであれば、付添人弁護士としては、強盗罪ではなく恐喝罪(原則逆送事件の対象外)が成立するにとどまるとか、窃盗罪と傷害罪が成立するにとどまるなどと主張して、事実関係の一部や法令の解釈・適用を争う事案が増えることが考えられる。これまでは、強盗であれ、恐喝であれ、事実関係自体に大きな争いがなければ、成人の刑事事件ほどには厳密に突き詰めて争わずに、保護観察か少年院か、といった点を重点的に議論していたものが、改正法の下では、適用される法令によって結論が大きく変わってしまうため、あえて争い、場合によっては被害者の尋問等を請求せざるを得ない場合も増えてくると思われる。
原則逆送事件の範囲拡大が、かえって被害者の負担を増加させ、少年の内省を遠ざけさせる結果となり得ることは明らかである。
55条移送
また、現行法の下でも、一度逆送された後に起訴された少年について、家庭裁判所が、これはやっぱり保護処分にするべきだ、と判断した場合には、事件を家庭裁判所に戻すことができるという規定がある。これは少年法55条に規定されているため、「55条移送」と呼んでいる。
最近でも、埼玉県で女性を監禁・暴行のうえ崖から突き落とす行為に加担した少年(当時15歳)について、逆送されて刑事事件となったものの、やはり保護処分が妥当であると言うことで家庭裁判所に移送された事案が報道されている。私自身も、以前に55条移送の決定をもらったことがある。
逆送の範囲拡大により、逆送事件が増えれば、その後の弁護人としては、あくまで保護処分を求めるため、刑事の公判において55条移送を求める事案が増えることが予想される。そうなると、必然的に事件終了までの期間が長期化することになる。時間が経つことで、少年の内省が薄れてしまう可能性もあるし、そもそも手続に長期間拘束すること自体が少年の健全育成を害することは明らかである。
このように、逆送の範囲拡大は、様々な副作用をもたらすことが懸念されるところであり、こうした副作用について十分な考慮が払われた形跡がないこと自体、少年事件の実情や少年法の実務を知らない人が頭の中だけで考えて作っていることが強く疑われるものである。
55条移送と実名報道
さて、改正案では、18歳、19歳の少年が逆送後に起訴された場合、実名報道を解禁するとの内容を盛り込んでいるという。これは重大な問題をはらんでいる。
実名報道によって、少年の再就職に支障が出るなどの問題は、既に繰り返し指摘されているが、最も深刻なのは、起訴後、刑事の公判を経て、やはり保護処分が妥当であるとして家庭裁判所に移送される可能性もあるのに、起訴された段階で実名報道されてしまうと取り返しがつかないという点にある。いったん、拡散してしまった情報は、後から完全に削除することは実際上、無理であるから、55条移送された時点で報道を禁止しても意味をなさない。
これについては、法制審議会では、「55移送は例外的なものだから仕方がない」といった議論がなされたそうである。暴論というほかない。
実は、2000年の少年法改正時、法案提出者は、原則逆送の規定を設けても、55条移送を積極的に活用すれば刑罰の賦課は避けられるから、原則逆送は刑罰の対象を必然的に増加させるわけではないと説明していたのである。つまり、原則逆送の規定は、55条移送が適切に機能することを前提として初めて合理性を有すると、立案担当者は考えていたはずなのである。
実際上も、現在の実務では、少年院送致決定などとは異なり、逆送決定それ自体に不服を申し立てることはできないとされている。このため、55条移送は、逆送決定の適法性・相当性を再審査する唯一の機会であると考えられている。55条移送によるチェックなくして、逆送の制度は正当化し得ないのであり、例外的だからという理由付けで実名報道との関係での調整を不要とするのは、これまでの改正経緯を完全に無視する不合理なものである。
まとめ
18歳、19歳の少年と言っても、実に様々である。中学を出てからすぐに働いて、既に一家の大黒柱になっているような少年もいれば、鉛筆一本削るのも親にやってもらっていて、完全に親に依存しているような少年もいる。そうである以上、少年非行も様々で、18歳、19歳の起こした事件でも、本人の精神的な未熟さや、生育歴・家庭環境など、まさしく少年特有の事情が深く影響している事案も多数存在する。
本稿を読んでいる皆さんも、警察のご厄介になったかどうかはともかくとして、「子どものしたことですから」「若気の至り」として、大人であれば許されないことでも大目に見てもらった、という経験をしたことが一度くらいはあるのではないかと思う。未発達な部分を残す少年については、根気強く見守ることが肝要であり、それが長い目で見れば社会全体のためにもなるのである。また少年事件については、家庭環境や生育歴などに問題があることがほとんどであり、貧困や児童虐待のように、少年自身の努力によってはどうしようもない要因が強く影響していることもある。筆者が担当した事件でも、「こういう家庭環境で育てば、自分でも非行のひとつやふたつするだろうな」と思ってしまう事件が決して少なくない。
最近の調査で、東大生の家庭は総じて世帯年収が高いことが明らかにされており、世間では、いい親に当たるかそうでないかをソーシャルゲームのガチャに例えて「親ガチャ」と呼ぶのが流行っている。ガチャで外れを引いたことで、非行に走らざるを得なかった少年を責めても詮無いことである。
むしろそうした少年を社会的に排除することなく、教育的なアプローチを行うことによって包摂することが重要であるのに、そうした選択肢を狭めるような改正は、ますます「生きづらい」社会を作ることにつながっていく。今回の少年法改正が、そもそも誰の利益になるのか、それとも害を及ぼすのか、目先の短絡的な感情論に惑わされることなく、立ち止まって慎重に考える必要がある。
その他のコラム
弁護士VS税理士訴訟 仁義なき戦い 訴訟記録にあたってみた結果

X(Twitter)共有&フォローお願いします! Tweet Follow @mizuno_ryo_law はじめに 所得税に関する助言の誤りを理由に弁護士が税理士に対して損害賠償を請求した事案である東京地判令和4年5月16日令和2年ワ11869号が、ネットを中心に話題となっている。 これまでに同裁判例に関して公刊されている文献を見ると、税務通信令和7年4月14日号「実例から学ぶ税務の核心 第...
持続化給付金不正受給に関する続報
令和3年1月19日に、続報 福岡で持続化給付金詐欺の摘発相次ぐという記事で、福岡県で持続化給付金不正受給による摘発が相次いでいることをお伝えした。 今回、さらに、福岡県警が同様の事案を摘発した。 こちらをご覧いただきたい。 持続化給付金詐欺の疑い 19歳の少年ら4人逮捕 福岡県 逮捕段階ということもあるので、名前については*に置き換えた。 詐欺の疑いで逮捕されたのは、福岡市城南区に住む建設作業...
【無抵抗・無条件降伏】B型肝炎訴訟弁護団横領事件裁判傍聴記【ヒーローのなれの果て】

X(Twitter)共有&フォローお願いします! Tweet Follow @mizuno_ryo_law はじめに 以前に紹介した事件の続報である。 B型肝炎訴訟熊本弁護団における横領事件について現時点で分かっていることをまとめてみた(2024/1/16 19:30更新) B型肝炎弁護団横領事件の続報 【予告するのはホームランだけにしてくれ】 【速報】B型肝炎訴訟弁護団長逮捕 ...
B型肝炎弁護団横領事件の続報 【予告するのはホームランだけにしてくれ】
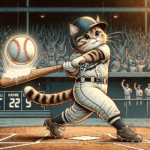
はじめに 以前に紹介した B型肝炎訴訟熊本弁護団における横領事件について現時点で分かっていることをまとめてみた(2024/1/16 19:30更新) これについての解説動画はこちら 【圧倒的独裁】B型肝炎訴訟熊本弁護団で発生した横領疑惑について思うこと【絶対的権力は絶対に腐敗する】 に関連して、とんでもない続報が入ってきた。 令和6年1月30日付熊本日日新聞の報道によると、熊本県弁護...
最決令和7年1月27日令和5年(あ)422号 組合活動に際して行われた犯罪に関する共謀の成否

判旨 原判決が是認する第1審判決の認定及び記録によれば、本件各行為は、被告人が執行委員長であったA労働組合B支部(以下「B支部」という。)が、バラセメント等の輸送運賃を引き上げることにより輸送業務に従事する運転手らの労働条件の改善を図るとの目的の下、近畿地方におけるバラセメント等の輸送業者の輸送業務を一斉に停止させること等を意図して、多数の組合員を動員して組織的に行った活動(以下「本件活動」という。)の一環であるところ、...