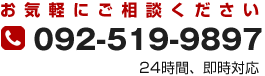弁護士VS税理士訴訟 仁義なき戦い 訴訟記録にあたってみた結果

X(Twitter)共有&フォローお願いします!
はじめに
所得税に関する助言の誤りを理由に弁護士が税理士に対して損害賠償を請求した事案である東京地判令和4年5月16日令和2年ワ11869号が、ネットを中心に話題となっている。
これまでに同裁判例に関して公刊されている文献を見ると、税務通信令和7年4月14日号「実例から学ぶ税務の核心 第104回 東京地判令和4年5月16日 税理士損害賠償請求事件」などがある。そこでは、かなり税理士に同情的な論調になっており、中には、「そもそも私なら、弁護士を関与先にするのは考えますね。」(白井一馬税理士発言)などと、弁護士の確定申告業務を受任すること自体にリスクがあるという趣旨の発言まで見られたところである。
そこで、当職は、本件紛争の実態についてより詳細に検討すべく、東京地裁に訴訟記録の閲覧に赴き、訴訟記録を全部読んでみた。その内容をもとに当職なりに見解をまとめたのが本稿である。
結論から言うと、本件はかなり特殊な事案であり、弁護士一般が税理士に対してクレームを寄越す存在であることを裏付けるものではないと考える。他方、弁護士以外の顧客であっても、税理士に対して同様のクレームが寄せられる可能性は十分ありうるところであり、事前の十分な防衛策が必要であると考えさせられる事案であることが分かった。
なお、本稿は、訴訟記録をもとに当職において事実認定を行っている部分や、当職が訴訟記録の内容をもとに独自に調査を行った結果を反映させている部分があり、裁判所の認定する事実のみに依拠しているわけではなく、また裁判所の認定事実と一致しない点も含まれることはあらかじめお断りしておく。また、原告である弁護士の行動について批判的な記載をする部分があるものの、当該弁護士個人について攻撃する趣旨ではないので、本稿をもとに原告に対して誹謗中傷や人格攻撃などを行うことはやめていただきたいと言うことをお伝えしておきたい。
また、上記税務通信の記事は、以後「税務通信」と略称する。
前提事実
訴訟記録やそれをもとにした調査の結果、本件に関する事実関係は以下のようなものであった。
当事者及び関係者の関係性
1 原告Xは、東京と大阪に事務所を構える大手法律事務所勤務の弁護士(63期)である(なお令和4年に別の事務所に移籍している)。専門は知的財産分野であり、税務訴訟などの経験はほぼない。
2 訴外亡Mは、税理士である。被告Y1はMの夫で税理士、被告Y2はMの子で、企業法務等を専門分野とする弁護士である。
3 訴外Lは、Xの当時の勤務先法律事務所に勤務する弁護士であり、Y2と司法修習で同期・同じクラスであった。Xよりも修習期は上である。
MがXの税務業務を受任した経緯
1 Xは、大阪勤務から東京勤務になったため、それまでの自宅を売却して転居することとなり、関東地方での新居の購入を検討していた。
2 また、Xは、東京勤務になった後にXの確定申告業務を行ってくれる税理士を探していた。
3 Mは、息子であるY2の修習同期である弁護士の確定申告業務を「お友達価格」で複数請け負っており、Lもそのことを知っていた。
4 XがLに東京で確定申告業務を行ってくれる税理士を探していることを相談したところ、Lが修習同期の弁護士の母親が格安で確定申告業務をやっているなどとして、Mを紹介した。
5 上記のような経緯もあり、平成29年度から、MはXの確定申告業務を年10万円で引き受けていた。
本件の経過
1 Mは、Xが自宅を売却した際に、居住用財産の譲渡特例を適用した。その際、Mは、Xに対して、本件は平成29年の申告としてもよいものの、書類を揃えるなどの負担もあるので平成30年の申告として処理する旨伝えた。Xは、このことを承諾したものの、内心では、税理士の都合で申告を遅らせたのではないかと考えていたようである。
2 その後、Xは、令和元年10月29日に、Mにメールを送付して、自宅の購入を考えているが、以前に譲渡特例を使っているので併用はできるのかといった趣旨のメールを送信した。これに対して、Mは、同年10月30日、3年以内譲渡についての期間制限があるので、転居は令和3年以降に行わなければ控除は受けられないと返答した。
3 すると、Xは、同日、Mにメールを送信して、では令和2年に転居した場合、2年目以降(令和3年以降)の控除を受けることは可能であるか、不動産業者を通じて税務署に確認したところそのような返答であったという趣旨のことを述べた。これに対し、Mは、2年目以降から控除を受けられるわけではないとした上で、Xの自宅売却に関する税務申告は、本来であれば平成29年度の申告とすることもできたのであるから、今から修正申告を行って平成29年に譲渡特例を受けたという体裁にすれば、令和2年に自宅を購入して転居したとしても住宅ローン特別控除を受けられると回答した。
4 Xはこれに応諾し、Mに対して修正申告の事務手続の見積もりを求め、Mは3万円と回答した。
5 Xは、11月5日、Mにメールを送信し、不動産を購入するかどうか早期に決めなければならないなどとして、Mに対して修正申告を急ぐよう求め、Mは11月6日に、申告書はできているのですぐに提出できると回答した。これに対して、Xは、今週中に新居の購入を決めると伝えた上で、11月8日に、Mに対して、家を買うことにしたので修正申告をお願いしたい、これで住宅ローン特別控除が全額受けられるのかなどとメールで尋ねた。Mが大丈夫であると回答すると、Xは来週早々に修正申告を行ってほしいと要請した。
6 11月11日、Mは修正申告書を提出した。
7 しかし、11月22日、MはXに対し、本件は修正申告の要件を充足していないので、受け付けられないとして税務署から修正申告を拒絶されたとしてXに謝罪した。
8 これに対して、Xは、Mに対して、メールで、「これは大問題ですよ」などと抗議し、既に不動産屋に手付金500万円を払ってしまった。経緯を説明してもらいたいので事務所に来てもらいたいなどと要求した。Mは、Xに対してさらに謝罪し、本件の修正申告費用は全額返金すると回答した。
訴訟提起に至るまで
1 Xは、Xを債権者、Mを債務者として、債権仮差押え命令を申立て、同命令は令和元年12月19日に発令された。
2 Y2は、Mから、預金が引き出せなくなったなどとして相談を受けたことにより、MとXとの紛争を知るに至った。そこでY2は、Xの紹介元であるLに、MとXとの紛争について相談した。
3 Lは、事務所の後輩と同期の母親との紛争であるため、なるべく穏便に解決しようと考え、Xを執務室に呼び出した上で、XがMとトラブルになっていることについて確認し、「解決できるのであれば、自分(L)の方で支払をする」などと申し出た。これに対して、Xは、「とても払える額ではない」などと返答した。
4 その後、令和2年1月16日に保全異議の申立てがなされたものの、1月23日にMが死亡し、仮差押えについては和解により終了した。
5 最終的に、令和2年5月11日に本訴が提起された。本訴においては、当初、税理士の助言ミスを理由とする損害賠償に加えて、Y2に対して、XとMとの紛争を勝手にLに話したことがプライバシー侵害にあたるとして、プライバシー侵害を理由とする100万円の損害賠償請求も併合提起されていたが、こちらは後に取下げられた(詳細な経緯は訴訟記録からは読み取れず)。
訴訟の経過や判決については、判決書原文や税務通信を参照されたい。
考察
1 税務通信の税理士発言に見られる違和感の正体
(1)本件において、MのXに対するアドバイスに間違いがあったこと自体は、Yらも積極的に争ってはいない。問題は、これによってXが住宅ローン特別控除を受けられなくなったことについて、M(実際には相続人であるYら)が、果たしてどこまで責任を負わなくてはならないのかという点にある。
Yらは、訴訟において、MがXから受任していたのはあくまで申告業務のみであり、節税対策などを行う顧問業務は含まれないと主張していた。確かに、Mの税理士報酬は、年額10万円と極めて安価(というよりあってないようなものだろう)であり、本件の修正申告費用も3万円と、ほぼ名目的な対価に留まっている。税務通信の岡野訓税理士発言が、「この中でやりきれないのは、報酬3万円で修正申告を行っている点ですね。なにせ、このやり取りの直後に、弁護士は住宅を購入しています。1億円近い物件の購入の意思決定の相談ですから、なんというか。」と慨嘆しているのは、やはり税理士報酬が安すぎるということを表している。
その程度の報酬で、節税スキームの提案や相談までさせられるとなるとたまったもんじゃないよというのは、心情としては十分に理解できるところである。
(2)しかしながら、裁判所はそのようには考えなかった。「納税義務者から委任を受けて税務申告をするに当たっては、単に一定の申告業務をするにとどまらず、納税義務の適正な実現に向けて、その申告業務が関係法令等に適合するものであるか否かを十分に確認、調査すべき義務を負っている」とされたわけである。
(3)弁護士業務もそうであるが、報酬が安ければ責任が軽くなると言うわけではないので、この点は肝に銘じておく必要がある。
2 「友達価格」の落とし穴
(1)従って、税理士としては、確定申告業務を受けるとしても、上記のような調査・確認義務が発生することを前提に、適切な税理士報酬を設定する必要がある。税務通信の内藤忠大税理士発言にあるように、「元々住宅ローン特別控除は、近年の改正による複雑化もあり、税理士にとっては落とし穴になる論点です。その点を意識すると、十分な報酬をもらって詳細な検討をしないと、怖くて仕方がありません。もちろん、その値段では税理士に頼まないということもあり得るでしょうけれど、それはやむを得ない気がします」というのは全くもってその通りである。
(2)本件は、Mが息子Y2のために同期の弁護士の確定申告業務を格安で引き受けていたという事情があったようである。しかしながら、もちろん、友達価格だからとか、知り合いだからと言って責任が軽減されることにはならないので、親しき仲にも礼儀ありというけれども、知り合いだからこそ適切な報酬を設定するということを忘れてはならない(もちろん、通常の価格から1-2割程度割引するといった程度のサービスはあり得るであろう)。
しかも、本件において、XはY2の直接の知り合いではなく、間にLを挟んでおり、友達ではなく「友達の友達」である。昔、故鳩山邦夫氏が、「私の友人の友人がアルカイダ」といって物議を醸したが、友人の友人まで範囲が広がると、人となりなどがよく分からない人物が紛れ込むリスクは大である。これは税理士に限ったことではなく、士業全般や一般のビジネスでも同様であるが、紹介案件だからと言って油断することなく、顧客については慎重に調査・検討することの重要性を改めて認識すべきである。
Mは、息子であるY2のためということもあって、好意で格安での業務を引き受けていたようであるが、1-2年目の新人弁護士であればともかく、それなりの年次で消費税を納付するくらいの売上の弁護士であれば、適正な税理士報酬を支払うことに経済的な問題はないはずである。そこを一円でも安く抑えたいと考えるような人物は、弁護士でなくても要注意な顧客であると言えよう。そういう意味でも、適正な税理士報酬を請求することは重要である。弁護士業務でも、「初回相談無料」や「法テラス利用」などに拘泥する依頼者はリスクが高いことが経験知として知られている。
3 委任契約書を作成して委任の範囲を明確に!
(1)本件の一番の問題点は、Xとしては、税務に関すること全般をMに委ねているという認識だった一方で、Mはあくまで格安で確定申告業務を代行しているだけであり、節税スキームの提案や相談と言った税務顧問業務まで行うものではないという認識だったという、双方の考え方のズレが大きいように思われる。実は、Lも紹介する際にそのような説明をXに対して行っていたようである。
(2)弁護士と依頼者との紛争も、委任の範囲が不明確であることが原因となることが多い。このこともあり、弁護士職務基本規程では、委任契約書の作成が原則として義務づけられている。もっとも、委任契約書が存在しても、契約書の文言が曖昧なままだと、結局、疑義を生じることになりかねない。
(3)税理士の場合、委任契約書作成の義務まではないため、実際には口約束でなんとなく済ませているところも多いようである。しかしながら、本件のような紛争を防止するためには、委任契約書において委任の範囲を明確に定めておくことが必要不可欠である。助言の誤りと同等か、あるいはそれ以上にMがうかつだったのが、知り合いの紹介ということで、この点を閑却していたことにあると思われる。実際に、本訴において委任契約書は証拠として提出されておらず、そもそも作成されていなかったのではないかと推測される。
4 訴訟にまでなった背景
(1)とはいえ、本件類似のトラブルは、全国でもそこまで珍しいものではないと思われ、それが訴訟にまでなったという点において特異な事案であると思われる。ではなぜそこまで話がこじれたのだろうか。
(2)本件においてXは、最終的に訴訟を提起しているわけであるが、その前段階をみても、紹介元であるLの取りなしに対して「到底払える額ではない」などとして反発し(夫婦で税理士をやっていて息子が弁護士であるMに関してそのような発言はいささか失礼なようにも思われる)、それどころか、Mの預金に仮差押えをした上に、Lに取りなしを依頼したY2の行為をプライバシー侵害であるとして別途、損害賠償を請求するに至っている(陳述書において、Xは、「Y2がLを利用して本件を丸め込もうとしている」「自分は被害者なのに同僚にトラブルについて言いふらされて苦痛を受けた」といった趣旨の供述をしている)。
(3)これらの手続ひとつひとつは、違法なものではないし、そのような手続を選択したXの判断が悪いとか、誤っているとか、非難に値するということはできない。しかしながら、知り合いの紹介で委任し、それなりの期間お世話になっていた税理士に対して、十数年で500万円程度の節税効果が見込まれるに留まる住宅ローン特別控除に関して、そこまでするだろうかという違和感はある。そもそもの問題として、自宅の購入はすみかを設定するために行うもので、住宅ローン特別控除が受けられることは至上命題ではないはずだ。
Xの行為は、結果的に紹介元であるLの顔を完全に潰す格好になっているわけで、LはYらの側に立って陳述書の作成や尋問(結局採用されなかったが)への協力まで行っている。他方で、Xは本件の住宅購入に際して約1億円のローンを組んでおり、大手法律事務所勤務であることからすると、相応の収入があるものと思われる。
弁護士業務をしていると、数百万円の弁護士費用を依頼者に踏み倒されるといったことも時折見られ、そのこととのバランスを考えると、わざわざ紹介元の顔を潰して訴訟提起してまで回収しなければならないような損害なのだろうかという気もする。
(4)また、弁護士であれば、預金に対する仮差押えによって、自営業者である税理士の業務にどれほど重大な支障が生じるのかについては容易に想像がつくところであり、他方で、YらはMの相続放棄をせずに訴訟を受継していることから考えると、仮差押えまでする必要があったのだろうかという疑問もある。Mによる助言のミスが判明した令和元年11月22日から、仮差押え命令の発令日である12月19日まで1箇月もないことを踏まえると、本件では事前交渉がほとんどなされずに、いきなり仮差押えが行われたことが推認され、Xの強硬な姿勢が強くうかがわれるところである。
(5)そうした点を踏まえると、税務通信白井税理士発言の「そもそも私なら、弁護士を関与先にするのは考えますね」といった結論に至ることも、税理士のリスク管理としては致し方ないようにも思われる。しかしながら、全弁護士がこのように税理士のミスに対して強硬な手段に出るかというと、そんなことはないであろう。
(6)また、税務通信では、「依頼者である弁護士は、この段階で、周到に確認しています。」(白井発言)「本件、依頼者である弁護士の周到さ、そして、税理士側の対応の脇の甘さが目立つ気がしますね。」(岡野発言)など、あたかも、Xが最終的には住宅ローン特別控除相当額の経済的利益をMからの損害賠償で賄うために布石を打っていたかのような発言が見られるところである。しかしながら、この点に関しては、当職が訴訟記録を検討する限り、確かにそうした疑いがあること自体は否定できないものの、明確にそうであるという確証を得られるだけの証拠は見いだせなかった。
(7)ところで、東京や大阪などの大都市はともかく、地方都市になればなるほど、税理士との付き合いの重要性は全弁護士の共通認識である。通常は、ロータリーやライオンズクラブ、商工会議所等の経営者団体を通じて知り合った税理士とか、小中学校時代からの付き合いのある税理士、信頼できる共通の知り合いがいる税理士などに依頼することがほとんどであり、単に税務業務を依頼するだけに留まらず、相続案件などで税理士に相談したり、顧客を紹介したり、あるいは逆に紛争案件の紹介を受けたりといった「持ちつ持たれつ」の関係にあることが多いと思われる。そうした税理士に対して、いくら弁護士でも、一度の失敗をあげつらって仮差押えや訴訟をしていたら、その訴訟で勝てたとしても、他の部分において多額の機会損失が発生するだけでなく、コミュニティにおける立ち位置にもよくない影響が生じると言えよう。また、その税理士との契約が終了したとして、ひとたびミスをすれば仮差押えまで仕掛けてくると言った噂が立つと、今後の申告業務を引き受けてくれる税理士がいなくなるのではないかという懸念もありうるところである。
これはムラ社会的な道徳観の故に正当な権利行使が妨げられているとかそういった話ではなくて、純粋に、そのことについて訴訟に踏み切ることの利害得失を冷静に計算した上での帰結である。国家間の争いでも、こちらにいくら正義があっても、あえて戦争を仕掛けずに交渉して場合によっては譲歩すると言った選択がしばしばとられるが、それと同様である。
(8)逆に言うと、そうしたコミュニティによるつながりが希薄な大都市圏においては、弁護士の依頼を受けるに際しては特に注意が必要であるとも言える。やはり訴訟や仮差押え等の法的手続を熟知している以上、やろうと思えばすぐに動けるからである。
ただ、別に弁護士に限った話ではなく、税理士に対して同様のクレームや損害賠償の請求を行う依頼者というのは、サラリーマンだろうと中小企業の社長だろうと同様に想定しうる。従って、やはり税務業務を受任する場合に、顧客の属性やキャラクターに注意を払うべきであるということは当然であると言えよう。税務通信の村木慎吾税理士発言にある、「言葉は悪いですが、付き合う相手を選ぶ、そのための目を養うことが、税理士業務で生きていくために最重要かもしれませんね。」という点は、全くもってその通りであると思う。
まとめ
確かに本件において、税理士の助言に誤りがあったことは疑いなく、また現在の裁判所の考え方を前提にする限り、一定の責任は免れないところではある。
しかし本件が訴訟提起に至るまで深刻化した背景には、大都市ならではの顧客対応の難しさや、Xの強硬な姿勢と言った特殊事情を抜きにして考えられるものではなく、税務通信の言うように弁護士全般が高リスクの要注意な依頼者であるというような考え方には直ちに賛同できない。
もっとも、本件においては、そもそもの受任時から紛争発生後の対応に至るまで、税理士の側にも今にして思えば見直すべきところが多数あり、税理士業務を行うに際しての大切な教訓を提供してくれるもののように思われる。
また、税理士に限った話ではなく、弁護士その他の士業や一般企業等に関しても全く同様で、①顧客を見極めることの重要性、②仕事(委任)の範囲を契約書等で明確化しておくことの重要性といった、基本的ではあるものの重要な原理原則に今一度立ち返ることの大切さを教えてくれる事例であるといえる。
X(Twitter)共有&フォローお願いします!
Follow @mizuno_ryo_law
事務所ホームページ https://mizunolaw.web.fc2.com/index.html
刑事事件特設サイト https://mfuklocriminaldiffence.com/
医療事件特設サイト https://mfuklomedical.com/
離婚事件特設サイト https://mfuklorikon.com/
Twitter  / mizuno_ryo_law
/ mizuno_ryo_law
弁護士ドットコム https://www.bengo4.com/fukuoka/a_4013…
弁護士ドットコム 相続事件特集 https://www.bengo4-souzoku.com/office…
ヤバい事務所に気をつけろ!
Part.1~Part.4
Part.1 ヤバい事務所のヤバすぎる実像 ![]() • 【法科大学院生 司法修習生 若手弁護士必見】ヤバい事務所に気をつけろ! P…
• 【法科大学院生 司法修習生 若手弁護士必見】ヤバい事務所に気をつけろ! P…
Part.2 日本よ、これがヤバい事務所だ! ![]() • 【法科大学院生 司法修習生 若手弁護士必見】ヤバい事務所に気をつけろ! P…
• 【法科大学院生 司法修習生 若手弁護士必見】ヤバい事務所に気をつけろ! P…
Part.3 今日からできる!ヤバい事務所の見分け方 ホームページはかく語りき ![]() • 【法科大学院生 司法修習生 若手弁護士必見】ヤバい事務所に気をつけろ! P…
• 【法科大学院生 司法修習生 若手弁護士必見】ヤバい事務所に気をつけろ! P…
Part.4(完) 間違ってヤバい事務所に入ってしまったら? 辞めることに一片の躊躇無し!!!
ヤバい事務所に気をつけろ!2
![]() • 【法科大学院生 司法修習生 若手弁護士必見】 ヤバい事務所に気をつけろPa… 弁護士の現実とは⁉現役弁護士3人が忖度なしで話し合う座談会!(エントラストチャンネルゲスト出演)
• 【法科大学院生 司法修習生 若手弁護士必見】 ヤバい事務所に気をつけろPa… 弁護士の現実とは⁉現役弁護士3人が忖度なしで話し合う座談会!(エントラストチャンネルゲスト出演)
事務所ホームページ 刑事事件特設サイト https://mfuklocriminaldiffence.com/
医療事件特設サイト https://mfuklomedical.com/
離婚事件特設サイト https://mfuklorikon.com/
その他のコラム
【衝撃】裁判官インサイダー疑惑【それはバレるだろう】

金融庁に出向中の裁判官がインサイダー取引を行っていたという疑惑が浮上した。 インサイダー取引の規制に関する証券取引等監視委員会の異常なまでの自信や、弁護士業界におけるインサイダー規制などについて、元監査法人勤務のうぷ主が解説する。 業務で知った企業の内部情報をもとに株取引をした疑いがあるとして、金融庁に出向中の裁判官が、証券取引等監視委員...
接見のグルメ 早良署
福岡県警早良署は、その昔「西警察署」と呼ばれていた。福岡市は、昭和57年に当時の西区が西区、早良区、城南区に分けられたため、早良区に西警察署が置かれるという状況が長く続いていた。平成18年に、当時の西署が早良署となって早良区及び城南区を管轄し、新たにJR今宿駅付近に西警察署が設置され、西区を管轄することになった。このため、西警察署の建物は新しいが、早良警察署の建物はかなり古い(昭和47年頃に築造されたようである)。 早良...
不見識極まりない検察官 薬物事犯における一部執行猶予を巡る目を疑うような主張

はじめに 昨今、検察官の質の劣化が指摘されて久しい。当地においても例外ではなく、証拠開示の遅延、書面の提出期限を守らないといった手続的な側面から、尋問における拙劣な質問や、自ら秘匿決定を申し立てておきながら、質問の中で被害者のプライバシーを自ら口にするなど、枚挙に暇がない。 そのような中、本件では、検察官の業務の中でも最もメジャーな部類に属する薬物事犯の情状立証において、法に対する無理解、無知を露呈するとしかいいようの...
【速報】ベトナム人技能実習生による死体遺棄被告事件の控訴審判決について【これでいいのか】

はじめに 令和4年(2022年)1月20日、福岡高裁で注目すべき判決が言い渡された。ベトナム人技能実習生が、出産(死産)した児(双子)を遺棄したとして死体遺棄罪に問われた事件の控訴審判決である。 本稿では、同判決に関するこれまでの報道経過や、判決内容を報告する弁護団の記者会見における発言等を踏まえ、現時点で可能な分析を試みる。 事案の概要 被告人Yは、ベトナム国籍を有するベトナム人女性(日本語はほとんど話せ...
立川ホテル殺人事件 少年の実名報道を繰り返す週刊新潮に抗議する
繰り返される暴挙 東京都立川市にあるラブホテルの一室で、デリヘル嬢が19歳の少年に刺殺され、男性従業員が重傷を負うという事件が発生した。この事件については、当事務所のコラムでも取り扱った。 さて、この事件に関して、週刊新潮6月17日号は、「凶悪の来歴」「70カ所メッタ刺し!立川風俗嬢殺害少年の「闇に埋もれる素顔」」などと題して、少年の実名と顔写真を大々的に掲載した。 週刊新潮が、少年事件において、少年法61条を無視して少...