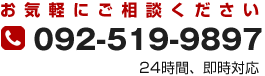一部執行猶予
執行猶予とは、有罪判決の場合に、判決を直ちに執行することなく、しばらく様子を見ることを言う。簡単に言えば、今すぐ刑務所というわけではなくて、しばらくの間、社会の中できちんとやっていけるかどうか様子を見て、大丈夫そうならそのまま社会で暮らしてください、というものである。法律上は、罰金にも執行猶予は可能であるが、実際に使われることは稀である。
さて、平成28年6月1日から、刑の一部執行猶予と呼ばれる制度が始まった。これは「一部」というだけあって、執行猶予のミニチュア版みたいに思われがちである。しかし実際には似て非なるものであり、また多くの問題をはらんでいる。
一部執行猶予を理解しやすいように、具体的な例で見てみよう。「被告人を懲役3年に処する。その刑のうち1年について、5年間執行を猶予する」という判決を受けた場合、これが確定したときに被告人はどうなるのか。
懲役3年の有罪判決であるものの、そのうち1年は執行が猶予されるため、3年から1年を除いた2年間は実刑であり、刑務所に行く必要がある。刑務所で2年間服役すると、一旦釈放され、そこから5年間は執行猶予ということで様子見となる。5年間のうちに何も問題がなければ、残りの1年は服役しなくてもよいということになる。ちなみに、法律上、この執行猶予の期間には、保護観察を付けることができるとされており、多くの場合は保護観察に付されているようである。
つまり、当たり前と言えば当たり前であるが、一部執行猶予というのはあくまで服役することが前提であり、出所の時期を裁判所があらかじめ定めると言った意味合いに過ぎないのである。この意味で、社会における更生可能性を探るという全部執行猶予の本来の意味合いとは異なっている。
このことは、一部執行猶予制度がなぜ作られたか、ということとも関係している。平成10年代には、刑務所の定員が100%を超える状況が続いており、人手不足が深刻化していた。このため、刑務所収監者を減らすための方策として、フランスの制度を参考に用いられたわけである。つまり、成り立ち自体が、妥協の産物というか、政治的な配慮に基づくものなので、理論的に洗練されたものではないのである。
このため、一部執行猶予を巡っては、いくつか問題がある。
ひとつは、一部執行猶予となることが、被告人にとって本当に利益になるのか、ということである。
例えば、先ほどの「被告人を懲役3年に処する。その刑のうち1年について、5年間執行を猶予する」という判決の場合、被告人は2年間服役し、その後5年間は執行猶予であり、多くの場合は保護観察に付されるから、被告人は7年間、この事件とお付き合いをしなければならなくなる。保護観察になった場合、非行少年などと同様に、定期的に保護司との面談などをしなければならないので、面倒に感じる人も多いようである。仮に全部実刑であれば。3年間服役すれば満期出所になるので、長い目で言えば早く終えられるという考え方もあり得る。どちらが不利益なのかは、被告人の感じ方にもよるようであるものの、一概に服役期間が短ければよいというものでもないようである。
もうひとつは、どういう場合に一部執行猶予が選択されるのか、弁護士も予測がつかないし、裁判官も明確な基準を持っていないのではないかと思われることである。
一部執行猶予の要件は、全部執行猶予の場合と同様で、これに、前刑の執行猶予中の者が加えられている。全部執行猶予になる要件を満たしている人を、あえて一部執行猶予にするくらいなら、全部実刑にして刑期を短くすれば十分であるように思われるし、前刑の執行猶予中に再犯をした者は、ほとんどが実刑になるので、一部執行猶予を相当するような事案はほとんどないように思われる。
実際には、一部執行猶予については、「薬物使用等の罪を犯した者に対する刑の一部の執行猶予に関する法律」という法律が特例を定めており、実務上、一部執行猶予になるのはほとんどがこの法律が適用される事例である。この法律は、覚せい剤取締法などの一定の薬物犯罪を犯した者については、刑法上の一部執行猶予の要件を満たしていなくても、「刑事施設における処遇に引き続き社会内において規制薬物等に対する依存の改善に資する処遇を実施すること」が必要かつ相当である場合には、一部執行猶予とするというものである。
しかし、この特例は、具体的にどういう事案について一部執行猶予にするべきであるのかという点について、極めて曖昧な要件しか定めていないため、一部執行猶予になる場合とならない場合とを振り分ける基準が皆目、不明であるというのが正直なところである。裁判官によるばらつきが大きく、めったに一部執行猶予にしない裁判官もいれば、これを頻発する裁判官もいるという印象である。弁護人としても、要件を満たしていれば、とりあえず一部執行猶予が相当である旨の弁論をせざるを得ないため、事態はより混沌としている。
被告人にとって本当に利益になるのか分からない上に、基準も曖昧で理論的にも練られていないのが、今の一部執行猶予の実態である。早期に再考の機会が持たれてしかるべきであろう。
その他のコラム
【法科大学院生 司法修習生 若手弁護士必見】ヤバい事務所に気をつけろ! Part1

Part1 ヤバい事務所のヤバすぎる実像 セクハラ、パワハラ、オーバーワーク・・・ 世の中には、入ってはいけない弁護士事務所が厳然と存在する。 それは、スタッフの基本的人権を無視し、人間の尊厳をないがしろにするような職場だ。 そのような職場は、経営者に問題がある。 Part.1では、実際にあった事例を踏まえ、「ヤバい事務所」の実態を解説する。 リンク...
最判令和6年12月17日令和6年(あ)536号

判旨 所論は、令和4年法律第97号による改正前の組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(以下「法」という。)13条1項5号の規定について、正当な経済活動により得た財産をも没収することができるとしている点で憲法29条に違反すると主張する。しかし、本件は、被告人が、財産上不正な利益を得る目的で犯した商標法違反の犯罪行為により得た財産等を、その他の自己の財産と共に自ら管理する他人名義の銀行口座に預け入れ、もって犯罪...
続報 福岡で持続化給付金詐欺の摘発相次ぐ
先日よりお伝えしている持続化給付金詐欺について、当地、福岡で、逮捕者が続出している。3の報道記事を紹介する。なお、逮捕段階であることを考慮し、個人名については*にて置き換えた。 1月9日 西日本新聞 持続化給付金詐取の疑い 男2人逮捕 福岡県警 福岡県警は8日、新型コロナウイルス対策の国の持続化給付金をだまし取ったとして、詐欺の疑いで、自営業*(23)=住所不定、建設作業員*(32)=北九州市...
最判令和7年2月17日裁時1858号18頁 特別交付税の額の決定の取消訴訟が法律上の争訟にあたるとされた事例

事案の概要 本件は、地方交付税法15条2項の規定による特別交付税の額の決定に対する取消訴訟は、「法律上の争訟」に該当するとしてこれを適法であるとした事例である。 本件訴訟の背景として、国は、いわゆる「ふるさと納税」の返礼品が多額になるなど競争が過熱している現状に鑑みて、ふるさと納税の納付額が多い自治体の特別交付税を減額するという措置を執った。これに対してX(泉佐野市)が、取消を求めて出訴したものである。 第一審(...