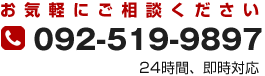最判令和6年12月17日令和6年(あ)536号

判旨
所論は、令和4年法律第97号による改正前の組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(以下「法」という。)13条1項5号の規定について、正当な経済活動により得た財産をも没収することができるとしている点で憲法29条に違反すると主張する。しかし、本件は、被告人が、財産上不正な利益を得る目的で犯した商標法違反の犯罪行為により得た財産等を、その他の自己の財産と共に自ら管理する他人名義の銀行口座に預け入れ、もって犯罪収益等の取得につき事実を仮装し、これにより生じた貯金債権が没収の対象とされている事案であるから、前記貯金債権の没収について適用されるのは、原判決が指摘するとおり、法13条1項6号である。したがって、所論は、犯罪収益及び犯罪収益に由来する財産の額又は数量に相当する部分を超えて、法10条1項前段の犯罪行為により生じた財産全体の没収を可能とする法13条1項6号の規定違憲をいうものと解される。
そこで検討すると、法は、犯罪による収益が組織的な犯罪を助長するとともに、これを用いた事業活動への干渉が健全な経済活動に重大な悪影響を与えることなどに鑑み、犯罪による収益の隠匿等を処罰するとともに、犯罪による収益の的確な剝奪を可能とするための没収及び追徴に関する特例等を定めることなどを目的としている。これを受けて、法10条は、犯罪収益とその前提となる犯罪との関係を隠すなどの行為が、将来の犯罪活動に再投資されたり、合法的な経済活動に悪影響を及ぼしたりするなどのおそれのある犯罪収益の保持・運用を容易にするものであることから、その行為自体の反社会性、法益侵害性に着目してこれを処罰することとし、犯罪収益又は犯罪収益に由来する財産が含まれる限り、前記のおそれがあることには変わりがないことなどから、これらの財産とこれらの財産以外の財産とが混和した財産の取得等につき事実を仮装し、又は混和した財産を隠匿した場合、その財産全体について仮装又は隠匿の罪が成立するとしている。その上で、法10条の犯罪行為に関わる財産について、法13条1項5号は、当該犯罪行為を組成した財産全体を、同項6号は、当該犯罪行為により生じた財産等を、それぞれ没収することができると規定している。
このように、取得等につき事実を仮装する行為や隠匿行為の客体となった財産全体について法10条の罪が成立するとした上で、同条の犯罪行為に関わる財産を広く任意的没収の対象とすることは、同条の犯罪行為を予防・禁圧するとともに、将来の犯罪活動に再投資されたり、合法的な経済活動に悪影響を及ぼしたりするなどのおそれのある財産の的確な剝奪を可能とするという、前記法の目的を達成するために必要かつ合理的な措置といえる。したがって、法10条の犯罪行為に関し、これにより生じた財産等を没収することができるとする法13条1項6号の規定は、憲法29条に違反しない。このように解すべきことは、当裁判所の判例(最高裁昭和26年(あ)第1897号同32年11月27日大法廷判決・刑集11巻12号3132頁、最高裁昭和37年(あ)第1243号同39年7月1日大法廷判決・刑集18巻6号290頁)の趣旨に徴して明らかである(最高裁昭和35年(あ)第1358号同36年3月30日第一小法廷判決・刑集15巻3号667頁参照)。
解説
本判決は、組織犯罪処罰法13条1項6号が憲法29条に反しないとしたものである。
組織犯罪処罰法13条1項6号は、同法9条(不法収益等による法人等の事業経営の支配を目的とする行為)、10条(犯罪収益等隠匿)、11条(犯罪収益等収受)により生じ、若しくはこれらの犯罪行為により得た財産又はこれらの犯罪行為の報酬として得た財産について、任意的に没収できると定めている。
没収の趣旨は、犯罪行為によって犯人に生じた利得を保持させない点にあるところ、本判決によれば、組織犯罪処罰法10条は、犯罪収益とその前提となる犯罪との関係を隠すなどの行為が、将来の犯罪活動に再投資されたり、合法的な経済活動に悪影響を及ぼしたりするなどのおそれのある犯罪収益の保持・運用を容易にするものであることから、その行為自体の反社会性、法益侵害性に着目してこれを処罰することとし、犯罪収益又は犯罪収益に由来する財産が含まれる限り、前記のおそれがあることには変わりがないことなどから、これらの財産とこれらの財産以外の財産とが混和した財産の取得等につき事実を仮装し、又は混和した財産を隠匿した場合、その財産全体について仮装又は隠匿の罪が成立するものであり、刑法に定める没収の趣旨を前進ないし発展させ、よりその実効性を高める意味合いがあるものと思われる。
特に、近年、仮想通貨や電子決済等によって、「財産」の概念は、物からデータへ、すなわち観念化する傾向にある。そのような経済情勢に応じて、マネーロンダリングの手法も多様化、巧妙化し、犯罪集団が巧みに財産をロンダリングすることで、不法な収益を保持するスキームも発達してきており、いわゆるイタチごっこの状況が続いている。かかる情勢にあっては、隠匿行為について犯罪収益とそうでない財産が混和したものについて、全体として犯罪収益隠匿罪が成立し、任意的没収の対象となること自体は、やむを得ないものであるということができよう。
もっとも、任意的没収については、無限定に没収できるわけではないことは勿論である。具体的な事案において、不相当に過大な範囲で没収がなされるようなことがあれば、かかる没収の判決は、法の趣旨を逸脱した違法なものとなるものと考えられる。
事務所ホームページ https://mizunolaw.web.fc2.com/index.html
刑事事件特設サイト https://mfuklocriminaldiffence.com/
医療事件特設サイト https://mfuklomedical.com/
離婚事件特設サイト https://mfuklorikon.com/
Twitter  / mizuno_ryo_law
/ mizuno_ryo_law
弁護士ドットコム https://www.bengo4.com/fukuoka/a_4013…
弁護士ドットコム 相続事件特集 https://www.bengo4-souzoku.com/office…
ヤバい事務所に気をつけろ! Part.1~Part.4
Part.1 ヤバい事務所のヤバすぎる実像 ![]() • 【法科大学院生 司法修習生 若手弁護士必見】ヤバい事務所に気をつけろ! P…
• 【法科大学院生 司法修習生 若手弁護士必見】ヤバい事務所に気をつけろ! P…
Part.2 日本よ、これがヤバい事務所だ! ![]() • 【法科大学院生 司法修習生 若手弁護士必見】ヤバい事務所に気をつけろ! P…
• 【法科大学院生 司法修習生 若手弁護士必見】ヤバい事務所に気をつけろ! P…
Part.3 今日からできる!ヤバい事務所の見分け方 ホームページはかく語りき ![]() • 【法科大学院生 司法修習生 若手弁護士必見】ヤバい事務所に気をつけろ! P…
• 【法科大学院生 司法修習生 若手弁護士必見】ヤバい事務所に気をつけろ! P…
Part.4(完) 間違ってヤバい事務所に入ってしまったら? 辞めることに一片の躊躇無し!!! ![]() • 【法科大学院生 司法修習生 若手弁護士必見】 ヤバい事務所に気をつけろPa…
• 【法科大学院生 司法修習生 若手弁護士必見】 ヤバい事務所に気をつけろPa…
事務所ホームページ
刑事事件特設サイト
https://mfuklocriminaldiffence.com/
医療事件特設サイト https://mfuklomedical.com/
離婚事件特設サイト https://mfuklorikon.com/
Twitter https://twitter.com/mizuno_ryo_law
その他のコラム
最判令和6年4月26日労経速2552号7頁(職種限定雇用契約と配転命令権)

事案の概要 本件は、公的機関の指定管理者として福祉用具の製作・開発等を行う財団法人Yに雇用されていたXが、XY間には技術職に職種を限定する旨の合意があるにも関わらず、総務課施設管理担当への配置転換を命じたことは違法であるとして、Yに対して損害賠償の請求などを行った事案である。原審は、Yの配置転換命令は配置転換命令権の濫用に当たらず、違法であるとはいえないとしてXの請求を棄却したため、Xが上告した。 判旨 「原審の確定した...
司法試験のPC入力への変更に思うこと 人間の能力は道具によって引き出される
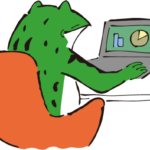
司法試験が手書きからPC入力へ 司法試験が、手書きによる答案作成からPC入力に移行するという報道がなされた。 私が司法試験を受けた頃は、受験用にモンブランのボールペンや万年筆を購入することも珍しくなかった。手が疲れるとか肩が凝るとか、実に意味のない苦労を強いられた。それがなくなるというわけだ。 方向性には基本的に賛成 だから、手書きを辞めてPC入力にするという方向性自体には、基本的に賛成である。...
【速報】福岡県感染拡大防止協力金詐欺事件で有罪判決【コロナ協力金詐欺】
持続化給付金
店舗を通常営業していたにもかかわらず、休業又は時短営業したかのように装って、福岡県感染拡大防止協力金を不正に受給した被告人らに対し、福岡地方裁判所(鈴嶋晋一裁判長)は、令和4年2月18日に有罪判決を言い渡した。 判決によると、被告会社Aの経営者である被告人B、及びその経理担当者である被告人Cは、被告会社Aが運営していた複数の飲食店について、実際には通常通り営業していたにもかかわらず、福岡県からの要請に従い、休業したなどと...
最判令和6年10月31日令和5年(受)906号 大学教員の任期

はじめに 本件は、大学の教員の職が大学の教員等の任期に関する法律4条1項1号所定の教育研究組織の職に当たるとされた事例である。 事案の概要 Xは、羽衣国際大学(Y:学校法人羽衣学園が設置、運営)人間生活学部人間生活学科生活福祉コース専任教員であった者である。 Yは、同コースの専任教員4名のうち1名が退任したことに伴い、後任の専任教員を募集していたところ、Xがこれに応募した。募集要項で...
「共同親権導入の結論ありきで議論を進めないでください」賛同人となりました

水野FUKUOKA法律事務所 離婚特設ページ 共同親権導入は「拙速」 弁護士ら法務省に申し入れ 法制審議会(法相の諮問機関)の家族法制部会で、離婚後の子どもの養育に関し父母双方の「共同親権」導入が検討されていることを巡り、各地の弁護士らが21日、導入は拙速だとする申し入れ書を法務省に提出した。その後、東京都内で記者会見し、ドメスティックバイオレンス(DV)や虐待のケースにどう対応するか話し合われないまま議論が進んでいる...