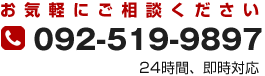最決令和6年10月16日令和6年(許)5号 取調べ録画媒体と文書提出命令

はじめに
本件は、検察官による取調べの録音録画記録媒体が法律関係文書に該当するとして文書提出命令の申立てがされた場合に、刑訴法47条に基づきその提出を拒否した国の判断が、裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用したものとされた事例である
事案の概要
本件の基本事件は、刑事事件で無罪となったXが、国(Y)に対して、国家賠償法に基づく損害賠償を請求する事案である。
不動産会社を経営するXは、学校法人Mから手付金名目で受領した金員を横領したとして、業務上横領の疑いで逮捕・勾留され、起訴された。公判では、Xが当該金員を貸し付けた先が、Mであると認識していたのか、Mの当時の理事長であったBであると認識していたのかが主要な争点となり、検察官は、Xが貸付先をBであると認識していたことの裏付け証拠として、共犯者として逮捕・勾留されたAの供述を挙げ、同人の証人尋問が実施された。しかし、Aは、当初の取調べにおいては、貸金の貸付先がB個人であるとの説明はしておらず、その使途は明浄学院の再建費用であると説明した旨の供述をしていたというものである。
最終的に、上記の点についてAの供述は信用できないとされ、Xには無罪判決が言い渡されて、その後確定した。
Xは、Aの取調べにあたったC検事が、Aを脅迫するなどの違法な取調べを行った結果、Aが虚偽の供述をするに至ったことなどを理由として、国家賠償請求を行った。その中で、上記の点を立証するため、Aの取調べの様子を録画した記録媒体について、民訴法220条3号に基づき文書提出命令の申立を行った。
なお、Xは、Aに対して、虚偽供述を行ったことなどを理由に不法行為に基づく損害賠償請求を行い、「本件本案訴訟において本件記録媒体が証拠採用されることを前向きに検討し、反対しないことを確認し、抗告人が、本件記録媒体中のAの顔にモザイクをかけ、声を加工し、プライバシー情報を出さず、報道機関に実名報道を避ける旨を申し入れるなど、Aのプライバシーの保護に最大限配慮することを確認すること等を内容とする訴訟上の和解」が成立している。
第一審は、記録媒体について、Xの公判に提出されたもののみならず、公判未提出の部分についても、Yに提出を命じた。これに対してYが抗告したところ、原審(大阪高決令和6年1月22日令和5年(ラ)1152号)は、公判未提出の部分については、刑訴法47条に基づいて提出を拒否したYの判断に裁量権の逸脱・濫用はないとして、申立を却下した。これを不服としてXが許可抗告した。
判旨
原決定取消し。Yの抗告棄却。
「本件の経緯に照らせば、本件供述は、抗告人が本件横領事件について逮捕、勾留及び起訴されるに当たり、その主要な証拠と位置付けられていたということができるところ、本件公判不提出部分は、検察官のAに対する取調べの過程を客観的に記録したものであること等からすると、抗告人と相手方との間において、法律関係文書に該当するということができる。」
「刑訴法47条は、その本文において、「訴訟に関する書類は、公判の開廷前には、これを公にしてはならない。」と規定し、そのただし書において、「公益上の必要その他の事由があって、相当と認められる場合は、この限りでない。」と規定しているところ、本件公判不提出部分は、同条により原則的に公開が禁止される「訴訟に関する書類」に当たることが明らかである。
ところで、同条ただし書の規定によって「訴訟に関する書類」を公にすることを相当と認めることができるか否かの判断は、当該「訴訟に関する書類」が原則として公開禁止とされていることを前提として、これを公にする目的、必要性の有無、程度、公にすることによる被告人、被疑者及び関係者の名誉、プライバシーの侵害、捜査や公判に及ぼす不当な影響等の弊害発生のおそれの有無等の諸般の事情を総合的に考慮してされるべきものであり、当該「訴訟に関する書類」を保管する者の合理的な裁量に委ねられているものと解すべきである。そして、民事訴訟の当事者が、民訴法220条3号後段の規定に基づき、上記「訴訟に関する書類」に該当する文書の提出を求める場合においても、当該文書の保管者の上記裁量的判断は尊重されるべきであるが、当該文書が法律関係文書に該当する場合であって、その保管者が提出を拒否したことが、民事訴訟における当該文書を取り調べる必要性の有無、程度、当該文書が開示されることによる上記の弊害発生のおそれの有無等の諸般の事情に照らし、その裁量権の範囲を逸脱し、又はこれを濫用するものであると認められるときは、裁判所は、当該文書の提出を命ずることができるものと解するのが相当である(最高裁平成15年(許)第40号同16年5月25日第三小法廷決定・民集58巻5号1135頁等参照)。このことは、当事者が提出を求めるものが、検察官の取調べにおける被疑者の供述及びその状況を録音及び録画を同時に行う方法により記録した記録媒体であったとしても異なるものではない。」
「ア これを本件についてみると、本件本案訴訟においては、抗告人が、AはC検事がAを脅迫するなどの言動をしたためにC検事に迎合して虚偽の本件供述をした旨を主張するのに対し、相手方が、AはC検事の説得により真実である本件供述をしたと評価し得る旨を主張して、Aが本件供述をするに至ったことに対するC検事の言動の影響の有無、程度、内容等が深刻に争われている。しかるところ、本件公判不提出部分には、C検事の言動がその非言語的要素も含めて機械的かつ正確に記録されているのであるから、本件本案訴訟の審理を担当する原々審が、本件公判不提出部分は本件要証事実を立証するのに最も適切な証拠であり、本件反訳書面や人証によって代替することは困難であるとして、本件公判不提出部分を取り調べる必要性の程度は高いと判断したことには、一応の合理性が認められ、このような原々審の判断には相応の配慮を払うことが求められるというべきである。
原審は、抗告人が主張するC検事の言動のうち当事者間に争いがあるものは、発言内容が重視されるものに限られる上、当該言動についても本件公判提出部分や本件反訳書面の取調べにより推認することができるとして、本件公判不提出部分を取り調べる必要性の程度は高いものではないと判断している。しかしながら、Aが本件供述をするに至ったことに対するC検事の言動の影響の有無、程度、内容等を受訴裁判所が判断するに当たって検討の対象となるのは、抗告人の主張において言語的に表現されたC検事の個々の言動に限られるものではなく、証拠に現れるC検事の言動の全てが上記の検討の対象となるものである。そして、C検事の言動がその非言語的要素も含めて機械的かつ正確に記録された本件公判不提出部分は、C検事の言動について、本件反訳書面や人証と比較して、格段に多くの情報を含んでおり、また、より正確性が担保されていることが明らかであるし、本件公判提出部分を取り調べることによって、本件公判不提出部分に係るC検事の言動のうち本件反訳書面に現れていないものを検討する必要がなくなると解すべき事情もうかがわれない。そうすると、この点について、原審の上記判断は合理的なものとはいえない。
そして、上記のとおり、原々審の上記判断には相応の配慮を払うことが求められることも踏まえると、原々審の上記判断のとおり、本件公判不提出部分を取り調べる必要性の程度は高いとみるのが相当である。
イ また、抗告人とAとの間に本件和解が成立し、本件和解において、Aが本件記録媒体の証拠採用に反対せず、抗告人もAのプライバシーの保護に最大限配慮することを明確に合意しているなどの本件の事実関係の下では、本件公判不提出部分が本件本案訴訟において提出されること自体によって、Aの名誉、プライバシーが侵害されることによる弊害が発生するおそれがあると認めることはできない。これに加えて、本件横領事件に関与したとされる者のうち、抗告人については無罪判決が確定し、抗告人以外の者について捜査や公判が続けられていることもうかがわれないことからすれば、本件公判不提出部分が本件本案訴訟において提出されることによって、本件横領事件の捜査や公判に不当な影響を及ぼすおそれがあるとはいえないし、将来の捜査や公判に及ぼす不当な影響等の弊害が発生することを具体的に想定することもできない。
ウ 以上の諸事情に照らすと、本件公判不提出部分の提出を拒否した相手方の判断は、その裁量権の範囲を逸脱し、又はこれを濫用するものというべきである。」
解説
刑事訴訟において入手した証拠については、目的外の使用が禁止されており、本件のように刑事手続に違法な点があったことを理由に国家賠償請求を提起するような場合も、目的外の使用に該当するものと理解されている。このため、そのような訴訟を提起する場合には、文書送付嘱託や文書提出命令などの手続を経て、改めて適法に証拠を入手する必要がある。
本件は、Aに対して検察官が違法な取調べを行った結果、Aが虚偽供述をするに至り、それを証拠としてXが逮捕・勾留の上訴追されたという事案ににおいて、Aの取調べを録音・録画した記録媒体の提出が問題となった事案である。
最高裁は、まず、取調べの記録媒体自体は、民事訴訟法220条3号の法律関係文書に該当し、文書提出命令の対象となること自体は認めつつ、刑事訴訟法47条本文の「訴訟に関する書類」にも該当すると判断した。そして、このような場合には、同条ただし書きに規定する場合を除いては、提出を拒否することができるとの解釈を前提に、「公益上の必要その他の事由があって、相当と認められる場合」に該当するか否かは、「これを公にする目的、必要性の有無、程度、公にすることによる被告人、被疑者及び関係者の名誉、プライバシーの侵害、捜査や公判に及ぼす不当な影響等の弊害発生のおそれの有無等の諸般の事情を総合的に考慮してされるべき」もので、書類を管理する者(通常は、国)の合理的な裁量に委ねられているとした。
その上で、本件においては、Aが本件供述をするに至ったことに対するC検事の言動の影響の有無、程度、内容等が深刻に争われているという本訴における争点を踏まえると、公判未提出の記録媒体にも、「C検事の言動がその非言語的要素も含めて機械的かつ正確に記録されているのであるから、本件本案訴訟の審理を担当する原々審が、本件公判不提出部分は本件要証事実を立証するのに最も適切な証拠であり、本件反訳書面や人証によって代替することは困難であるとして、本件公判不提出部分を取り調べる必要性の程度は高いと判断したことには、一応の合理性が認められ、このような原々審の判断には相応の配慮を払うことが求められる」とした、他方で、「抗告人とAとの間に本件和解が成立し、本件和解において、Aが本件記録媒体の証拠採用に反対せず、抗告人もAのプライバシーの保護に最大限配慮することを明確に合意しているなどの本件の事実関係の下では、本件公判不提出部分が本件本案訴訟において提出されること自体によって、Aの名誉、プライバシーが侵害されることによる弊害が発生するおそれがあると認めることはできない。これに加えて、本件横領事件に関与したとされる者のうち、抗告人については無罪判決が確定し、抗告人以外の者について捜査や公判が続けられていることもうかがわれないことからすれば、本件公判不提出部分が本件本案訴訟において提出されることによって、本件横領事件の捜査や公判に不当な影響を及ぼすおそれがあるとはいえないし、将来の捜査や公判に及ぼす不当な影響等の弊害が発生することを具体的に想定することもできない。」として、開示による弊害が具体的に想定しがたいことを指摘し、にもかかわらず提出を拒否した判断には、裁量権の逸脱・濫用があるとしたものである。
取調べ録画媒体について、結論として公判未提出の部分も含めて広範な提出命令を認めたという点において、本決定は評価できる。しかしながら、少なくとも捜査活動の違法性が争点となる国家賠償請求のような事案において、まさにその適法性を担保するための仕組みとして用いられている取調べ録画媒体を、国が広範な裁量に基づいて提出拒否できるというのは、本来的におかしな話である。
確かに、刑訴法47条ただし書きの文言は、「公益上の必要その他の事由があって、相当と認められる場合」という抽象的な要件しか掲げておらず、いかなる場合に当該要件を充足するのかについて、判断権者の裁量に委ねられているというのは、行政法規の解釈としては王道であると言える。しかしながら、刑訴法47条が、本件のように、捜査活動の違法性を問題として国家賠償請求がなされるという事態を十分に想定した上で規定されたものであるのかと言われると疑問である。このような場合、国としては、自ら行った捜査活動が適法であることについて、まずは一応の主張・立証を行ってしかるべきであり、その立証に用いる証拠について、自ら積極的に提出しないどころか、広範な裁量に基づいて提出を拒むというのでは、違法な捜査によって権利を侵害された者の救済としては不十分であると言わざるを得ない。
確かに、文書提出命令によって入手した証拠については、インターネットなどで拡散されることを防止するための十分な手当もないのであるから、それによって第三者のプライバシーが侵害される可能性も考えられる。しかしながら、捜査活動によって得られた証拠というのは、刑罰権の適正な行使を国民が監視するための公共財という性質もまた有しているのであるから、個人のプライバシー保護の要請は、その分後退するというのもやむを得ないのではないかとも思われる。少なくとも、国が第三者のプライバシーを錦の御旗として、自らの捜査活動の違法性を握りつぶすかの如き訴訟活動を行うことが不当であることは論をまたないところである。最高裁は、この点について、国の適切な裁量権行使に委ねればよいと安易に考えているフシがあり、要は公務員性善説とでも言うべき発想に立っているものと考えざるを得ない。昨今の再審無罪事件などで、検察官が自分たちに不利な証拠を徹底的に隠そうとしてきたという事実は、かかる公務員性善説に明確なNOを突きつける事象ではなかろうか。
立法論としては、文書提出命令を規定する民訴法220条において、刑事手続の違法を主張して国家賠償請求を行う事案について、刑事記録を幅広く提出させることができるような法改正を行うべきであると思われるし、刑訴法47条についても、国の適切な裁量権行使などが期待できないことは立法事実として明らかなようにも思われる(まさに本件がそのような事案である)ことから、原則と例外の規定を見直すことや、例外の要件を具体的に列挙することなども検討されるべきであろう。
事務所ホームページ https://mizunolaw.web.fc2.com/index.html
刑事事件特設サイト https://mfuklocriminaldiffence.com/
医療事件特設サイト https://mfuklomedical.com/
離婚事件特設サイト https://mfuklorikon.com/
Twitter  / mizuno_ryo_law
/ mizuno_ryo_law
弁護士ドットコム https://www.bengo4.com/fukuoka/a_4013…
弁護士ドットコム 相続事件特集 https://www.bengo4-souzoku.com/office…
ヤバい事務所に気をつけろ! Part.1~Part.4
Part.1 ヤバい事務所のヤバすぎる実像 ![]() • 【法科大学院生 司法修習生 若手弁護士必見】ヤバい事務所に気をつけろ! P…
• 【法科大学院生 司法修習生 若手弁護士必見】ヤバい事務所に気をつけろ! P…
Part.2 日本よ、これがヤバい事務所だ! ![]() • 【法科大学院生 司法修習生 若手弁護士必見】ヤバい事務所に気をつけろ! P…
• 【法科大学院生 司法修習生 若手弁護士必見】ヤバい事務所に気をつけろ! P…
Part.3 今日からできる!ヤバい事務所の見分け方 ホームページはかく語りき ![]() • 【法科大学院生 司法修習生 若手弁護士必見】ヤバい事務所に気をつけろ! P…
• 【法科大学院生 司法修習生 若手弁護士必見】ヤバい事務所に気をつけろ! P…
Part.4(完) 間違ってヤバい事務所に入ってしまったら? 辞めることに一片の躊躇無し!!! ![]() • 【法科大学院生 司法修習生 若手弁護士必見】 ヤバい事務所に気をつけろPa…
• 【法科大学院生 司法修習生 若手弁護士必見】 ヤバい事務所に気をつけろPa…
事務所ホームページ
刑事事件特設サイト
https://mfuklocriminaldiffence.com/
医療事件特設サイト https://mfuklomedical.com/
離婚事件特設サイト https://mfuklorikon.com/ 
Twitter https://twitter.com/mizuno_ryo_law
その他のコラム
司法試験のPC入力への変更に思うこと 人間の能力は道具によって引き出される
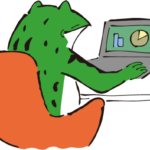
司法試験が手書きからPC入力へ 司法試験が、手書きによる答案作成からPC入力に移行するという報道がなされた。 私が司法試験を受けた頃は、受験用にモンブランのボールペンや万年筆を購入することも珍しくなかった。手が疲れるとか肩が凝るとか、実に意味のない苦労を強いられた。それがなくなるというわけだ。 方向性には基本的に賛成 だから、手書きを辞めてPC入力にするという方向性自体には、基本的に賛成である。...
教職員によるスマホの没収は適法か?
「子どもが学校で「スマホ」を没収されました…進級するまでと言われましたが、スマホは「解約」した方がいいでしょうか?」 このような教師がいるとすれば、言語道断の対応である。 学校の教師には、授業中にスマホで遊ばないようにする限度で一時的にスマホを取り上げる権限はあっても、それ以上にスマホを保護者に返還しないなどの権限はない。 合理的な理由もなく保護者に返さない場合は不法行為が成立しうるし、自分でそのスマホを遊びに使うなどすれ...
続報 持続化給付金詐欺 の判決まとめ5 背景事情の多様化 20210917
はじめに 持続化給付金の不正受給について、一般の方や、全国で同種事案の弁護人をされる先生方の参考になるよう、持続化給付金の判決について、情報収集を行い、分析を続けている。前回の記事から、さらにいくつかの判決に関する情報を入手した。 これまでの過去記事は以下をご覧いただきたい。 続報 持続化給付金詐欺 の判決まとめ4 徐々に増える実刑判決 20210804 続報 持続化給付金詐欺 の判決まとめ3 不可解な地域...
【勝手に出すな】会長声明ってなんだ【偏った思想の垂れ流し】

X(Twitter)共有&フォローお願いします! Tweet Follow @mizuno_ryo_law 文字起こし 弁護士の水野です。今日はですね、ちょっとライトな動画で、「会長声明って何なんだ?」という話をしていきたいと思います。 報道で、神奈川県の座間市で起こった連続殺人事件の被告に対して、死刑が執行されたという報道がありました。それに対して、日本弁...
「共同親権導入の結論ありきで議論を進めないでください」賛同人となりました

水野FUKUOKA法律事務所 離婚特設ページ 共同親権導入は「拙速」 弁護士ら法務省に申し入れ 法制審議会(法相の諮問機関)の家族法制部会で、離婚後の子どもの養育に関し父母双方の「共同親権」導入が検討されていることを巡り、各地の弁護士らが21日、導入は拙速だとする申し入れ書を法務省に提出した。その後、東京都内で記者会見し、ドメスティックバイオレンス(DV)や虐待のケースにどう対応するか話し合われないまま議論が進んでいる...