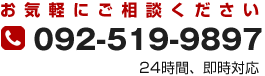立川ホテル殺人事件 少年の実名報道を繰り返す週刊新潮に抗議する
繰り返される暴挙
東京都立川市にあるラブホテルの一室で、デリヘル嬢が19歳の少年に刺殺され、男性従業員が重傷を負うという事件が発生した。この事件については、当事務所のコラムでも取り扱った。
さて、この事件に関して、週刊新潮6月17日号は、「凶悪の来歴」「70カ所メッタ刺し!立川風俗嬢殺害少年の「闇に埋もれる素顔」」などと題して、少年の実名と顔写真を大々的に掲載した。
週刊新潮が、少年事件において、少年法61条を無視して少年の実名などを掲載するという行為は今に始まったことではなく、出版社が組織的に行っていることは疑いない。
これについては、日弁連が、既に「少年の「推知報道」を受けての会長声明」において意見を表明しているところであるが、本稿では、少年法61条の趣旨とは違った観点から、週刊新潮の記事(以下、「本件記事」という)の問題点を明らかにする。
実名報道をする目的や必要性が不明確である
本件記事は、1頁を用いて少年の実名が掲載された顔写真を載せており、これはどうやら卒業アルバムから転用したもののようである。また、その次頁においては、「中学校生活を通して」と題する少年が作成した卒業文集が、頁の上半分を用いて全文、掲載されている。しかしながら、このように、大々的に顔写真や実名を掲載することの必要性や目的について、本件記事は十分な説明をしているとは言い難い。
一応、記事を見ると、「本誌が実名、顔写真を公開したのは、事件の重大さに鑑みて、かつ、被害者の個人情報ばかりが報じられることへの違和感や疑念を禁じ得ないためである」との説明がなされている。しかしながら、事案が重大であることと、少年の実名を報道しなければ報道の目的が達せられないこととの間に合理的な関連性はないし、被害者の個人情報が大々的に報じられているからと言って、少年の個人情報を流布することが許容されるという根拠はどこにもないから、この説明は論理的に誤っている。
そもそも、デリヘル嬢が勤務中に殺害されたという事案にもかかわらず、被害者の個人情報を扇情的に報道しているのは他ならぬメディア自身であるのに、それに対する批判・検証や自制を呼びかけるでもなく、それなら少年の個人情報も、といって公開するというのは、ただのマッチポンプである。
記事の内容も事件報道とはほど遠いゴシップばかりである
その後、20頁から始まる特集記事をみても、本件記事が、果たして何を目的に書かれたものであるのか、皆目不明である。
まず、記事では事案の概要が書かれ、その後に少年の中学時代から、事件直前までの様子が同級生や職場の同僚などによって語られる。とはいえ、記事の内容の主眼は、「割り箸を割らずに2膳使う」などと、少年がいわゆる「コミュ障」であり、仕事が長続きしなかった、奇行が目立っていたといった内容ばかりであり、事件とは無関係な少年の私生活に関する話題ばかりである。到底、実名を公開してまで明らかにすべき事実関係であるとは考えられず、事件に対する検証や再発防止策など、建設的な要素は皆無の、ただのゴシップが羅列されているに過ぎない。
一個人の違和感や疑念と言った主観的感情で出版社が法を犯してよいのか
また、本件記事では、先に述べたのに加えて、「やはり、彼を保護されるべき少年扱いすることには違和感を覚えざるを得ない」などとして、実名報道を正当化しようとする文章が見られる。これを見る限り、本件記事は、執筆者の個人的な義憤に端を発しているのではないかと疑わざるを得ないところである。しかしながら、個人のブログやTwitterであればともかく、署名な雑誌媒体が、そうした一個人の違和感や疑念といった主観的感情を後押しして、少年法61条というメディアに課せられた重大な法的規制をあえて犯すというのは、余りにも理性を欠いている。
週刊新潮は少年法61条違反を反復継続している
新潮社がこのような違法な実名報道を行うのは、今に始まったことではない。かつては、神戸連続児童殺傷事件において少年の顔写真を公表し、作家の灰谷健次郎氏がこれに激怒して、自らの版権を全て引き上げるという形で抗議に出たことがある。最近でも、名古屋市で発生した女子大生による殺人事件や、川崎市で発生した中学生殺害事件などで、少年の実名報道を行い、そのたびごとに各所から抗議を受けている。
記事において、少年法61条の趣旨を踏まえてもなお、実名を公開しなければ報道目的を達成できないような必要性が語られるでもなく、こうした野次馬根性を煽るだけの目的で少年の個人情報を全世界に拡散することには、何らの正義もありはしない。むしろ、少年に対するリンチを煽動しているものと評価されてもやむを得ない。
週刊誌の没落
しかしながら、今回、問題となった記事を入手しようとして、ひとつ気付いたことがあった。週刊新潮を購入しようとしても、コンビニに雑誌が全然売っていないのである。何軒か回って、ようやく発見したというのであるから、週刊誌というメディアが社会に与える影響力は、近年、着実に低下しているといえる。しかも最近では、地方都市に週刊誌が届くまでの日数が長期化していると言うから、読者の手に渡る頃には情報としての価値が陳腐化しており、インターネットをはじめとするメディアには、ますます太刀打ちできなくなっていると言えよう。
そのようななかにおいて、今一度自らの存在価値を問い直すことは重要である。にもかかわらず、大衆を煽るようなこうした違法・不当な記事を拡散し続けることが、報道機関としての職責を果たしている行為であるとは到底考えられない。
その他のコラム
【SSR来る】初接見遅延と福岡県警を提訴 当番弁護士、交通権侵害を主張【当番弁護士】

X(Twitter)共有&フォローお願いします! Tweet Follow @mizuno_ryo_law お問い合わせは、LINE友だち追加が便利! 事務所ホームページ https://mizunolaw.web.fc2.com/index.html 刑事事件特設サイト https://mfuklocriminaldiffence.com/ 医療事件特設サイト ht...
一部執行猶予
執行猶予とは、有罪判決の場合に、判決を直ちに執行することなく、しばらく様子を見ることを言う。簡単に言えば、今すぐ刑務所というわけではなくて、しばらくの間、社会の中できちんとやっていけるかどうか様子を見て、大丈夫そうならそのまま社会で暮らしてください、というものである。法律上は、罰金にも執行猶予は可能であるが、実際に使われることは稀である。 さて、平成28年6月1日から、刑の一部執行猶予と呼ばれる制度が始まった。これは「一...
最判令和7年2月17日裁時1858号18頁 特別交付税の額の決定の取消訴訟が法律上の争訟にあたるとされた事例

事案の概要 本件は、地方交付税法15条2項の規定による特別交付税の額の決定に対する取消訴訟は、「法律上の争訟」に該当するとしてこれを適法であるとした事例である。 本件訴訟の背景として、国は、いわゆる「ふるさと納税」の返礼品が多額になるなど競争が過熱している現状に鑑みて、ふるさと納税の納付額が多い自治体の特別交付税を減額するという措置を執った。これに対してX(泉佐野市)が、取消を求めて出訴したものである。 第一審(...
持続化給付金不正受給で緊急の人材募集が行われていたことが発覚
持続化給付金の不正受給(詐欺)について 関わってしまった場合には、すぐに相談を! 持続化給付金100万円「詐欺」福岡で初の逮捕 続報 福岡で持続化給付金詐欺の摘発相次ぐ 既にこれらの記事において、持続化給付金の不正受給についてお伝えしてきた通りである。持続化給付金不正受給は、国に対する100万円の詐欺という重大な犯罪であり、組織的な関与が疑われる事案も少なくないことから、逮捕・勾留されるリ...
控訴審 新井浩文さんの事例をもとに考える
はじめに 俳優の新井浩文こと朴慶培さんについて、東京高裁は令和2年11月17日、懲役5年の実刑とした第一審判決を破棄し、懲役4年の実刑判決を言い渡した。今回は、刑事控訴審の構造や、本判決に関する検討を行うこととしたい。 控訴審の構造 日本では、3回、裁判が受けられるということは、小学校の社会科の授業などでも習うので、広く一般に知られている。しかし、ボクシングの試合などとは異なり、裁判の第一ラウンドから...